
目次
小学校とは
小学校は日本における6年制の義務教育の学校であり、満6歳から12歳までの児童に教育を施す初等教育機関です。
1872年(明治5年)に発布された学制における名称は小学校でしたが、1886年(明治19年)の小学校令により尋常・高等小学校に分けられ、1941年(昭和16年)から1946年(昭和21年)までは国民学校と呼ばれました。
戦後の学校教育法により修業期間が6年に定まりました。
学校教育法第29条には「小学校は心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする」と定められています。
児童は修業年数6年の間に基礎学力や社会性を身に着け、自立的に生きるための生活能力を学んでいきます。
小学校への入学

義務教育制度の定めにより公立小学校への入学は満6歳の誕生日以後における最初の学年の初め(最初の4月1日)からとされており、入学年齢は4月1日時点で満6歳に達していることが条件になります。
公立小学校は無受験で入学することができますが、私立小学校や国立小学校への入学には一般的に「お受験」と呼ばれている小学校試験が行われます。
小学校 年間行事
4月から7月に行われる小学校の主な年間行事には入学式、始業式、健康診断、春の遠足、プール開きなどがあります。
夏休みが終了した9月から12月にかけては運動会や小学校6年生の修学旅行、秋の遠足、音楽会などが行われます。
冬休み終了後の1月から3月には書き初め大会や終業式、卒業式などが行われます。
保護者向けの年間行事として年に数回授業参観日も設けられています。
導入が増えている学校公開週間
近年は保護者や地域住民向けに学校や児童達の学ぶ様子を見学する機会を提供する「学校公開週間」を導入する小学校も増えてきています。
これは保護者や地域の住民に学校教育の現状を理解してもらい、学校・家庭・地域での連携をより深めることを主な目的としています。
小学校 運動会

運動会は小学校の学校行事の一環として行われる運動競技の集会です。
1885年(明治18年)初代文部大臣に就任した森有礼が兵式体操を学校教育の一つとして導入以後、小学校の運動会が普及していったと言われています。
運動会は学習指導要領においては学校行事としての「健康安全・体育的行事」に位置づけられる特別活動にあたります。
主な競技種目には徒競走やリレー、鈴割りや玉入れ、綱引き、騎馬戦、棒倒し、組み体操などがあります。
小学校運動会の開催時期
10月10日が体育の日に当たることから小学校の運動会も秋に多く行われてきましたが、近年は開催時期を秋から春の5月から6月頃に移行する小学校が増えています。
春の開催が増えている要因として台風や天候不順による影響が比較的少ないことや児童達への熱中症対策、年間行事の分散化などが挙げられます。
問題視されている運動会の組み体操事故
小学校の運動会で行われる組み体操ではこれまで事故が多発しており、その安全性が問題視されています。児童達が何段にも積み上がる組み体操のピラミッドやタワーの規模が年々大きくなっていることが大きな要因とされています。
平成25年度に全国の小学校で起きた組み体操の事故は6345件。障害が残った事故は平成25年度までの31年間で88件にのぼり、死亡事故も報告されています。
安全性を重視して組み体操の規模を小さくする方針を打ち出した自治体が増えています。
2016年には千葉県柏市が組み体操を全面的に廃止し、大阪市は2019年度より組み体操のピラミッドとタワーを禁止する方針を打ち出しています。
小学校 ローマ字表
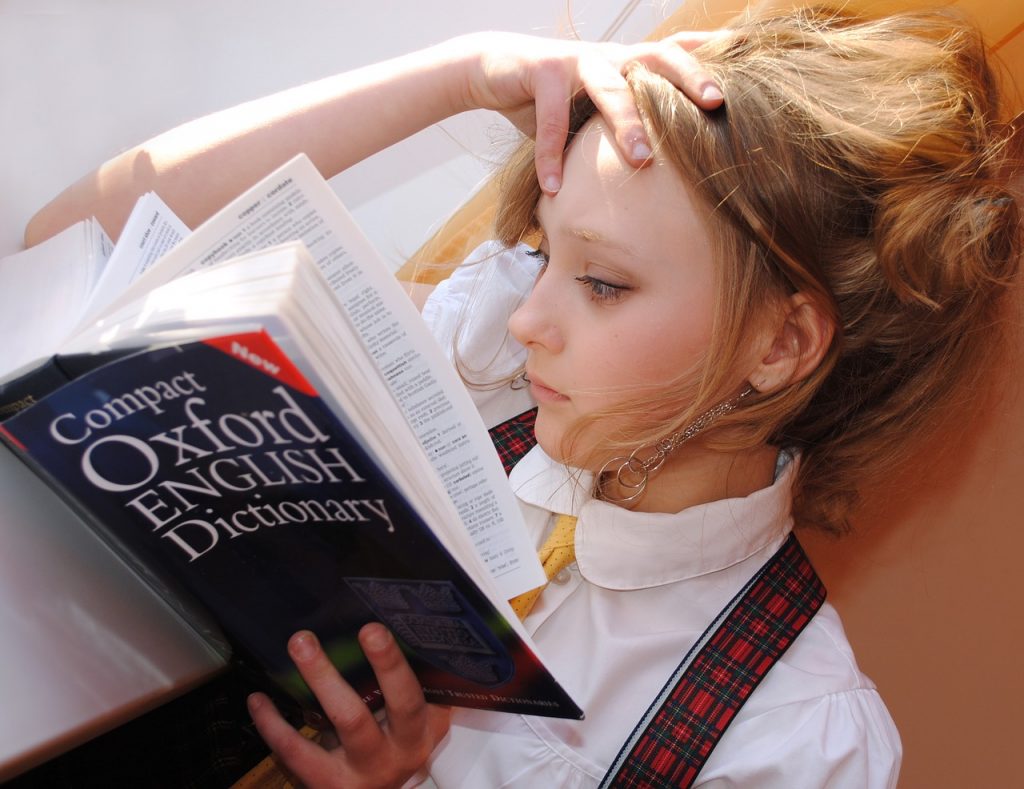
日常生活の中で児童がローマ字表記の本に触れたり、パソコンを用いた学習の機会が増えていることなどから公立小学校では3年生からローマ字を使った読み書きの指導が国語の授業内で行われます。
ローマ字表はローマ字を分かり易く一覧にまとめたものです。児童が覚えやすいようにお風呂のタイルや壁に水で貼ることができるローマ字表や下敷きになったローマ字表などのアイデア商品も発売されています。
小学校 時間割

文部科学省には学校教育法等に基づき各学校で教育課程(カリキュラム)を編成する際の基準を定めた「学習指導要領」があります。
各公立小学校はこの指導要領に基づいた時間割を組んでいますが、地域や小学校によって時間割は異なります。
公立小学校の始業時間は学校や地域によっても異なりますが、午前8時から8時30分頃までの時間帯としている小学校が多く見られます。
文部科学省は小学校の授業を45分、1単位としています。
小学校授業の各教科
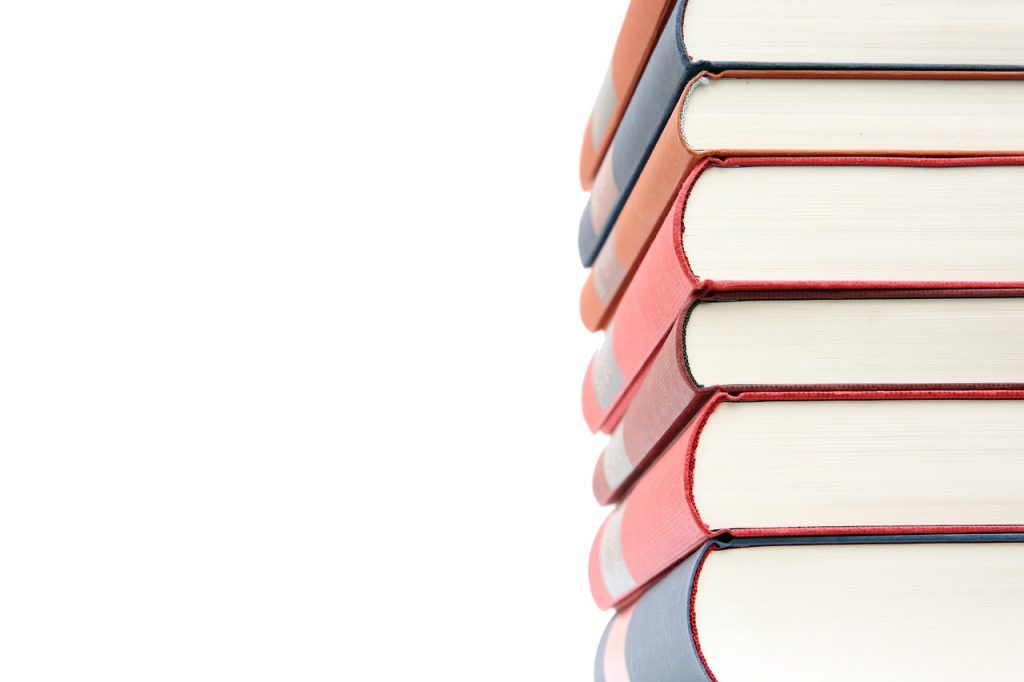
小学校の授業教科には国語、社会、算数、理科、社会、生活、音楽、図画工作、家庭、体育があります。
生活科は小学校1・2年次に学習する教科であり、小学校3年生から社会、理科の教科の履修が加わります。
さらに各教科に加えて道徳や特別活動の授業時数、総合的な学習の時間の授業時数、外国語活動の授業時数が加算されていきます。
小学校における英語教育
2008年度から小学5・6年生を対象に外国語活動として小学校の英語教育が開始、2011年度には小学校において新学習指導要領が全面実施され、小学校5・6学年で年間35単位時間の外国語活動が必修化されました。
文部科学省はグローバル時代に向け2020年度から実施予定の次期学習指導要領で小学校の英語教育を拡充することを発表しています。
これにより外国語活動の授業は小学校3・4年生に前倒しされ、小学校5・6年生では英語が教科化されることになります。